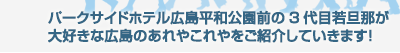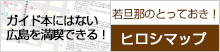若旦那の広島びいき - 時間ある方読んでみて下さい。
ヘッダーナビゲーション
時間ある方読んでみて下さい。2010/08/10 6:21 pm
こんにちは。
広島市内の観光地や、宮島の観光情報、広島県内の観光地を
ご紹介しておりますパークサイドホテル広島平和公園前の若旦那です。
友人が作ってくれた短編小説です。
なんだか感動しちゃいましたので、ご紹介します。
時間がある方読んでみて下さい。
ぼんやりし始めた記憶が8月の日差しに照らされ鮮明さを取り戻す。
あの角を曲がると、昔すんだアパートがある。
バスを降りて歩いてきたこの道も、12年まえ毎日のように歩いた道だ。
懐かしい街並の中に、新しい景色が混ざる。
時間は流れていく。
あのアパートはもうなくなっているのではないか、という気はしている。
それは予感と呼ぶには根拠がありすぎた。
まず何より、あのアパートは、12年前の時点ですでに老朽化が進みすぎていた。
床や柱は、所々朽ちかけていたし、階段は途中で抜けていた。
階段の暗い照明は、抜けた穴の中まで照らす事はなく、これがあの世の入口だと言われたら、そうかもしれないと言いたくなるような穴だった。
ただ、ボロいアパートだったけれど、不潔という訳ではなかった。
アパートの隣に住む大家のばあちゃんが毎日のように掃除をしていたので、ボロいアパートはいつもピカピカしていた。
アパートは気分しだいでボロボロだけどピカピカだと思えたり、ピカピカだけどボロボロだと思えたりした。
たぶんばあちゃんがいなければ、とおの昔にアパートは廃墟になったはずで、ばあちゃんが寿命のつきかけたアパートをなんとか支えていた。
そんなばあちゃんに、俺はなぜだか気に入られていて、ばあちゃんは、ことあるごとに「あんたはいつだって礼儀正しい」と褒めた。
褒められてはいたものの当時の俺は、自分の可能性だとか限界だとかが現実味をおびて降りかかってきた頃で、なんだか殻をやぶれないでいる自分を形容されているようで、複雑な気持ちだった。
そんなばあちゃんとは、あそこを離れてからもしばらく年賀状のやりとりだけはしていたのだけど、ある年、例年どうり年賀状を送ると、ばあちゃんが亡くなったという知らせがハガキ一枚で届いた。
その時、ばあちゃんと一緒にアパートも死んだんだと当たり前のように思った。
ばあちゃんとアパートは、俺の中では同じだった。
時間はそんなとこも昔にした。
それにしても、この道はこんなに長かっただろうか。
流れた時間が道を長くしたなんてことはないだろうと振り返ると、さっき降りたバス停が、それ程遠くもない場所にみえた。
気がつけば思った以上にゆっくりと歩いていたらしい。
そうさせたのは懐かしい景色か、それとも消えてしまっているかもしれないアパートのせいか。
俺は曲がり角に着いて立ち止まる。
そこにアパートがあろうとなかろうと、何かが変わることはないはずだ。
それでも、この気持ちを表現するなら不安ということになるのだろう。
俺は、目を閉じて一つ深呼吸でもしたように大きく息を吐くと、歩き出した。
ゆっくりと曲がり、そして視線をあげた。
真夏の太陽に照らされた街路樹の緑がまぶしい。その向こうに懐かしいアパートの姿がみえた。
アパートはあった。
12年?そんなにたったっけ?
とぼけたアパートの声が聞こえてきそうなほどアパートは記憶のままに変わっていないように見えた。
さらに近づくと、アパートはあの頃のようにピカピカだった。
懐かしい。
今にもばあちゃんがどこかから出てきて例によって俺を褒め始めそうなきがした。
夢でも見ているような心地でアパートの前に立っていると、後ろから誰かやってきた。
「ばあちゃん」思わず声を掛けそうになりながら振り向くと、そこには見たことのない若い女性が立っていた。年齢は20ぐらいだろうか。
話を聞けばばあちゃんの孫らしい。
俺は自分が昔ここに住んでいたことを伝えると、あれからのアパートとばあちゃんの話を聞いた。
ばあちゃんが死んで一度は取り壊しの話もでたアパートは、今は誰も住んではないが、この女性が今でも時々掃除にやってきているらしい。
女性は、アパートが取り壊されそうになった時の話を熱っぽく話していた。
アパートはおばあちゃんと同じ気がした、という彼女の想いは、俺のそれと似ていた。
聞けば俺がここにいた頃も、ばあちゃんに会いに来ていたらしく、そう言えばそんな娘を見た気もすれば見てない気もすると言うと、彼女も俺を見た気もすし見てない気もすると答えたので、二人で笑った。
最後に、ばあちゃんの話をしていると
「私、いつもおばあちゃんに誉められてたんです」
得意そうに彼女が笑う。「あんたはいつだって礼儀正しいって」
と彼女が言ったので俺は笑った。
(終)
広島市内の観光地や、宮島の観光情報、広島県内の観光地を
ご紹介しておりますパークサイドホテル広島平和公園前の若旦那です。
友人が作ってくれた短編小説です。
なんだか感動しちゃいましたので、ご紹介します。
時間がある方読んでみて下さい。
ぼんやりし始めた記憶が8月の日差しに照らされ鮮明さを取り戻す。
あの角を曲がると、昔すんだアパートがある。
バスを降りて歩いてきたこの道も、12年まえ毎日のように歩いた道だ。
懐かしい街並の中に、新しい景色が混ざる。
時間は流れていく。
あのアパートはもうなくなっているのではないか、という気はしている。
それは予感と呼ぶには根拠がありすぎた。
まず何より、あのアパートは、12年前の時点ですでに老朽化が進みすぎていた。
床や柱は、所々朽ちかけていたし、階段は途中で抜けていた。
階段の暗い照明は、抜けた穴の中まで照らす事はなく、これがあの世の入口だと言われたら、そうかもしれないと言いたくなるような穴だった。
ただ、ボロいアパートだったけれど、不潔という訳ではなかった。
アパートの隣に住む大家のばあちゃんが毎日のように掃除をしていたので、ボロいアパートはいつもピカピカしていた。
アパートは気分しだいでボロボロだけどピカピカだと思えたり、ピカピカだけどボロボロだと思えたりした。
たぶんばあちゃんがいなければ、とおの昔にアパートは廃墟になったはずで、ばあちゃんが寿命のつきかけたアパートをなんとか支えていた。
そんなばあちゃんに、俺はなぜだか気に入られていて、ばあちゃんは、ことあるごとに「あんたはいつだって礼儀正しい」と褒めた。
褒められてはいたものの当時の俺は、自分の可能性だとか限界だとかが現実味をおびて降りかかってきた頃で、なんだか殻をやぶれないでいる自分を形容されているようで、複雑な気持ちだった。
そんなばあちゃんとは、あそこを離れてからもしばらく年賀状のやりとりだけはしていたのだけど、ある年、例年どうり年賀状を送ると、ばあちゃんが亡くなったという知らせがハガキ一枚で届いた。
その時、ばあちゃんと一緒にアパートも死んだんだと当たり前のように思った。
ばあちゃんとアパートは、俺の中では同じだった。
時間はそんなとこも昔にした。
それにしても、この道はこんなに長かっただろうか。
流れた時間が道を長くしたなんてことはないだろうと振り返ると、さっき降りたバス停が、それ程遠くもない場所にみえた。
気がつけば思った以上にゆっくりと歩いていたらしい。
そうさせたのは懐かしい景色か、それとも消えてしまっているかもしれないアパートのせいか。
俺は曲がり角に着いて立ち止まる。
そこにアパートがあろうとなかろうと、何かが変わることはないはずだ。
それでも、この気持ちを表現するなら不安ということになるのだろう。
俺は、目を閉じて一つ深呼吸でもしたように大きく息を吐くと、歩き出した。
ゆっくりと曲がり、そして視線をあげた。
真夏の太陽に照らされた街路樹の緑がまぶしい。その向こうに懐かしいアパートの姿がみえた。
アパートはあった。
12年?そんなにたったっけ?
とぼけたアパートの声が聞こえてきそうなほどアパートは記憶のままに変わっていないように見えた。
さらに近づくと、アパートはあの頃のようにピカピカだった。
懐かしい。
今にもばあちゃんがどこかから出てきて例によって俺を褒め始めそうなきがした。
夢でも見ているような心地でアパートの前に立っていると、後ろから誰かやってきた。
「ばあちゃん」思わず声を掛けそうになりながら振り向くと、そこには見たことのない若い女性が立っていた。年齢は20ぐらいだろうか。
話を聞けばばあちゃんの孫らしい。
俺は自分が昔ここに住んでいたことを伝えると、あれからのアパートとばあちゃんの話を聞いた。
ばあちゃんが死んで一度は取り壊しの話もでたアパートは、今は誰も住んではないが、この女性が今でも時々掃除にやってきているらしい。
女性は、アパートが取り壊されそうになった時の話を熱っぽく話していた。
アパートはおばあちゃんと同じ気がした、という彼女の想いは、俺のそれと似ていた。
聞けば俺がここにいた頃も、ばあちゃんに会いに来ていたらしく、そう言えばそんな娘を見た気もすれば見てない気もすると言うと、彼女も俺を見た気もすし見てない気もすると答えたので、二人で笑った。
最後に、ばあちゃんの話をしていると
「私、いつもおばあちゃんに誉められてたんです」
得意そうに彼女が笑う。「あんたはいつだって礼儀正しいって」
と彼女が言ったので俺は笑った。
(終)